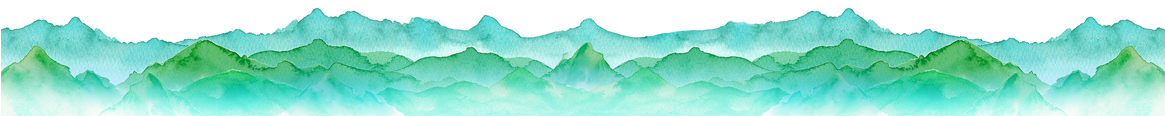レビー小体型認知症について

レビー小体型認知症は、英語では、dementia with Lewy bodiesといい、略して“DLB”と呼ばれます。レビー小体型認知症は、日本で見つけられた病気(脚注1)ですが、外国で注目されたのをきっかけに、最近日本でもよく知られるようになりました。アルツハイマー病に次いで、“第2の認知症”とも呼ばれています。
レビー小体型認知症の脳では、「レビー小体』という特殊な円形物質(神経細胞の中にある封入体と呼ばれるもの)が、中枢神経系を中心に多数見られます。このレビー小体が大脳皮質に広範に出現すると、その結果、レビー小体型認知症になります。
レビー小体型認知症は、認知症の一種ですので、記憶障害や理解力・判断力の低下等をきたします。ただし、初期から中期にかけては、記憶障害はあまり目立たず、幻視や認知の変動、パーキンソン症状、レム睡眠行動障害、抑うつ症状、自律神経症状など、特徴的な症状がさまざまに現れます。また、レビー小体型認知症は、薬に対する過敏性が高い(副作用が出やすい)ことも、特徴の一つです。その意味で、アルツハイマー型認知症などとは異なる点が多くあります。
脚注1:レビー小体型認知症は、故)小阪憲司先生の1976年以降の一連の研究報告によって、国際的に知られるようになり、小阪先生が提唱した「レビー小体病」や「びまん性レビー小体病(小阪病ともよばれます)を基礎としています。なお、レビー小体は、1914年にドイツの病理学者フレデリック・レビーにより発見されたものです。
引用:小阪憲司(2009)「知っていますか?レビー小体型認知症 よくわかる、病気のこと&介護のこと」メディカ出版小阪憲司・羽田野政治(2010)「レビー小体型認知症の介護が分かるガイドブック こうすればうまくいく、幻視・パーキンソン症状・生活障害のケア」メディカ出版